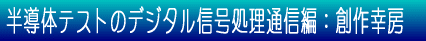自分で学ぶ半導体テスト入門セミナー1:技術者の自己啓発のために
| テストのための通信の標準技術を学ぶ ■技術力を見直す:量産工場や設計・評価の技術者のために 半導体工場に係わる技術者の学習のお役に立ちたいと考えています。生産や評価の効率化など改善のために通信の分野で標準的技術として使われているデジタル信号処理技術を学んでいきます。 このサイトは創作幸房の自分で学ぶ技術セミナーシリーズのNo5です。ここでは技術者が通信の標準技術:デジタル信号処理技術を自己啓発の一環として学べます。同時に実務としても半導体の量産や評価に欠かせない基礎知識として利用できます。 テスター構成は創作幸房の半導体量産テスト用の大型自動検査装置の経験に基いています。また資料の活用はご自身の判断と責任で使いいただけますようお願いいたします。 |
自己啓発として大切な基礎知識を磨き、見直す一環としてテスタによる通信のためのデジタル信号処理を検査や評価の実務にも使えるように学んでいきましょう。
これまでテスタによるデジタル信号処理技術のセミナーとして、
■テスタのためのデジタル信号処理の入門編
■テスタのためのデジタル信号処理の基礎編
■テスタのためのデジタル信号処理の実践編
と総集編を学んでいますが、今回は前回の総集編ではカバーしていなかった携帯電話に使われている半導体用に通信の基礎と応用を学びます。ぜひ学習の成果を実務に生かして下さい。
サイトの目次:
通信のためのデジタル信号処理
・デジタル信号処理の応用:変復調編
1.QPSKの変調
2.ATEによる変調応用例1
3.ATEによる変調応用例2
4.QPSKの復調
5.ATEによる復調応用例
6.EVMの定義
7.EVMの基本測定例
8.ATEによる側定応用例
・WCDMAの変調方式
1. 多元接続方式
2. スペクトラム拡散方式(送信)
3. スペクトラム拡散方式(受信)
4. スペクトラム拡散方式の無線伝送1
5. スペクトラム拡散方式の無線伝送2
6. WCDMAの変調方式1
7. WCDMAの変調方式2
8. WCDMAの変調方式3
9. ベースバンドの機器構成例
・復習1:テスタのためのデジタル信号処理の実践
1.テスタのマスタクロック(システム例)
2.AWGのサンプリングクロック設定
3.デジタイザのサンプリングクロック設定
4.サンプリングクロック、サンプリング数と測定周期の設定
5.FFTによるスペクトラム分析
6.マルチトーンによる信号発生と取り込み
7.高調波とスプリアス
8.分散処理などによるテストの高速化
9.並行処理によるテストの高速化
・復習2:半導体量産工場で使われている典型的なテスター構成例
1.デジタル信号処理ソース・キャプチャのアーキテクチャ
2.デジタル信号処理演算のアーキテクチャ
3.デジタル信号測定演算構成
| テスタのためのデジタル信号処理の通信応用編1. 携帯電話などに使われている通信用半導体の量産テストに必要な変復調のデジタル信号処理を学びましょう。 ・デジタル信号処理の応用:変復調編 1.QPSKの変調 2.ATEによる変調応用例1 3.ATEによる変調応用例2 4.QPSKの復調 5.ATEによる復調応用例 6.EVMの定義 7.EVMの基本測定例 8.ATEによる側定応用例 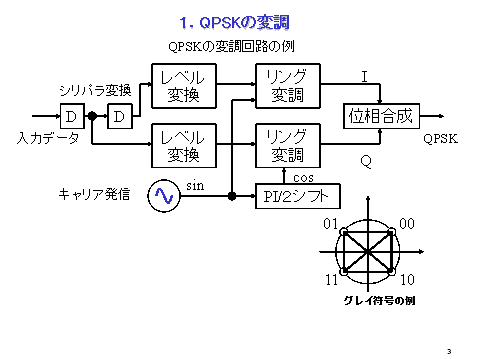 ■QPSKの変調回路の例 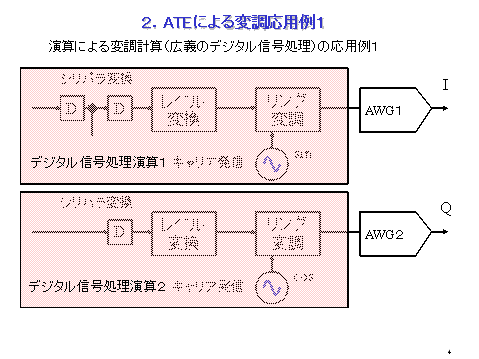 ■演算による変調計算(広義のデジタル信号処理)の応用例1 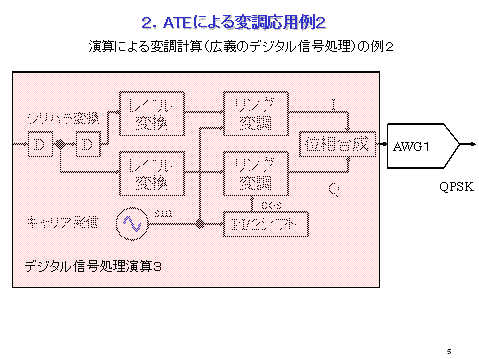 ■演算による変調計算(広義のデジタル信号処理)の応用例2 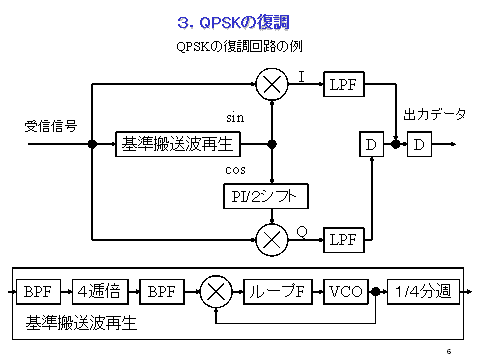 ■QPSKの復調回路の例 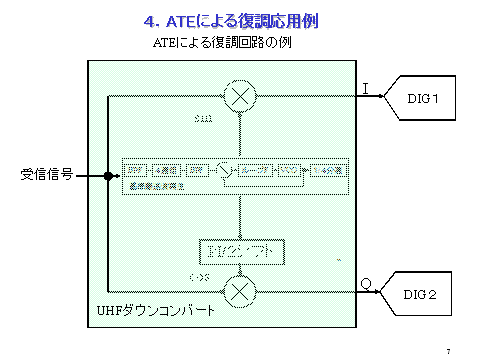 ■ATEによる復調回路の例 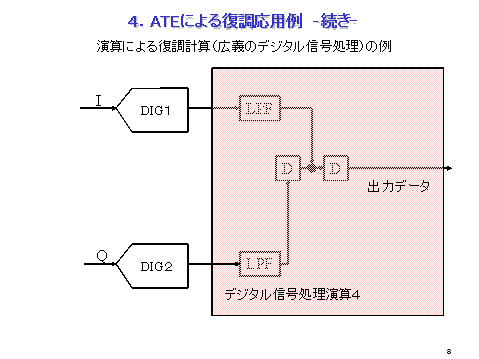 ■演算による復調計算(広義のデジタル信号処理)の例 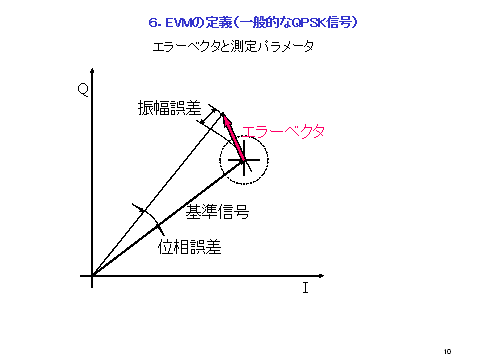 ■EVMの定義(一般的なQPSK信号) 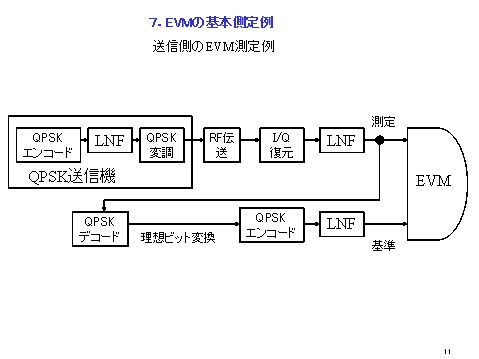 ■送信側のEVM測定例 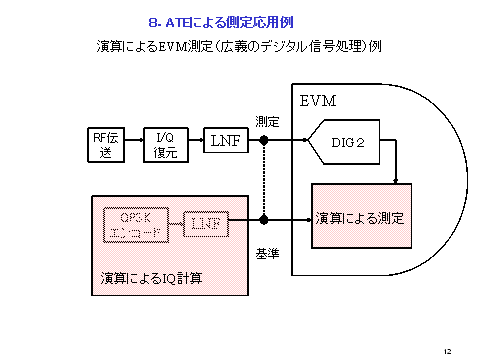 ■演算によるEVM測定(広義のデジタル信号処理)例 資料の活用に関してはご自身の責任で判断いただけますようお願いいたします。引用する場合はソースを明示していただけますようお願いいたします。 |
| テスタのためのデジタル信号処理の通信応用編2. 携帯電話などに使われている通信用半導体の量産テストに必要な変復調のデジタル信号処理を学びましょう。 ・デジタル信号処理の通信編:WCDMAの変調方式 1. 多元接続方式 2. スペクトラム拡散方式(送信) 3. スペクトラム拡散方式(受信) 4. スペクトラム拡散方式の無線伝送1 5. スペクトラム拡散方式の無線伝送2 6. WCDMAの変調方式1 7. WCDMAの変調方式2 8. WCDMAの変調方式3 9. ベースバンドの機器構成例 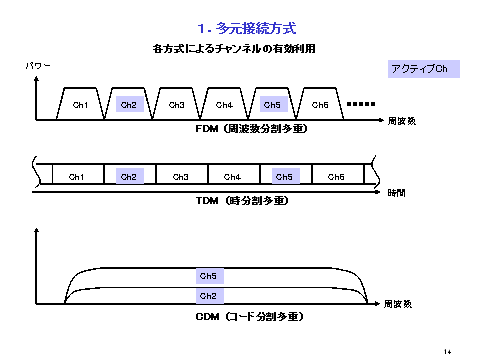 ■多元接続方式:各方式によるチャンネルの有効利用 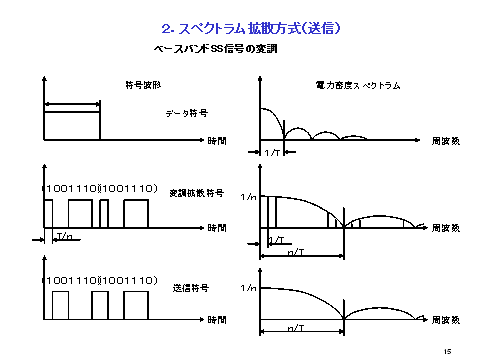 ■スペクトラム拡散方式(送信):ベースバンドSS信号の変調 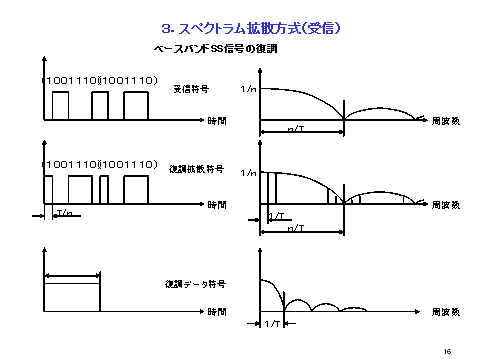 ■スペクトラム拡散方式(受信):ベースバンドSS信号の復調 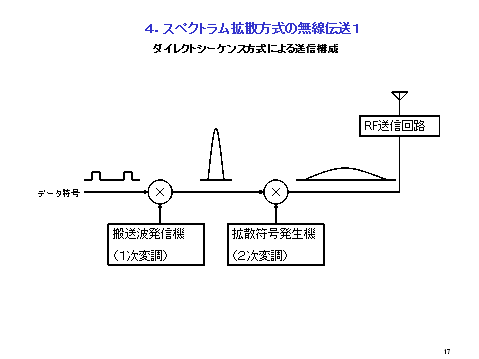 ■スペクトラム拡散方式の無線伝送1:ダイレクトシーケンス方式による送信構成 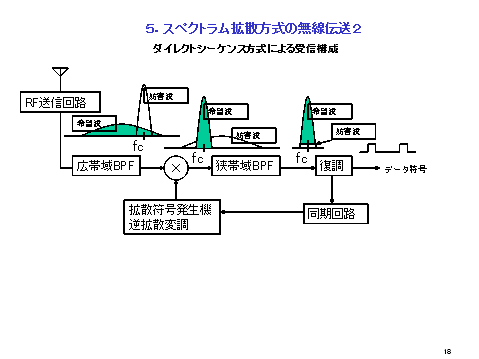 ■スペクトラム拡散方式の無線伝送2:ダイレクトシーケンス方式による受信構成 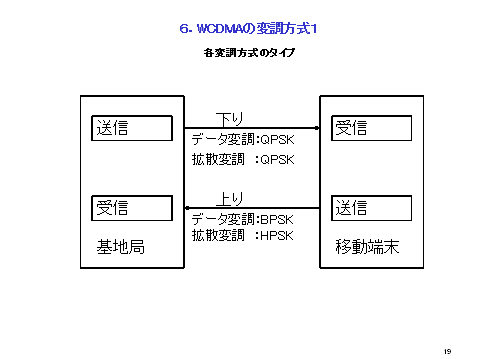 ■WCDMAの変調方式1:各変調方式のタイプ 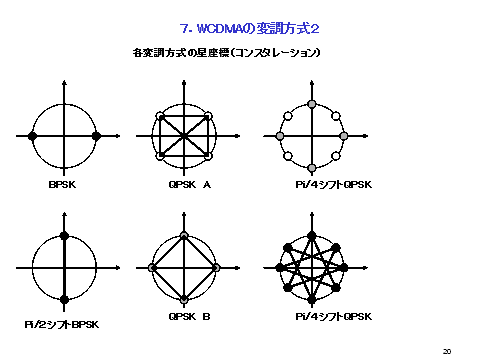 ■WCDMAの変調方式2:各変調方式の星座標(コンスタレーション) 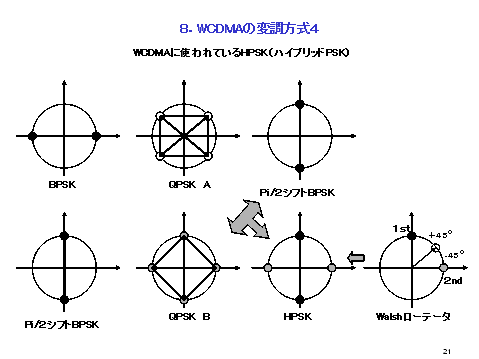 ■WCDMAの変調方式3:WCDMAに使われているHPSK(ハイブリッドPSK) 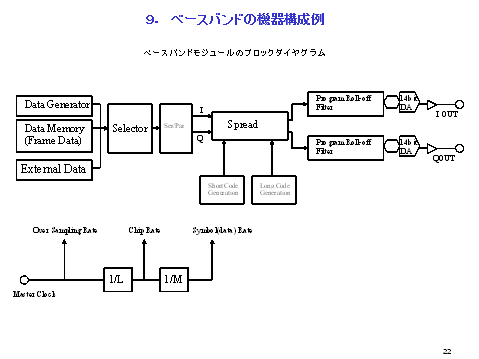 ■ベースバンドの機器構成例 資料の活用に関してはご自身の責任で判断いただけますようお願いいたします。引用する場合はソースを明示していただけますようお願いいたします。 |
| 復習1:テスタのためのデジタル信号処理の実践編 半導体量産テストに必要なデジタル信号処理演算を行うためのテスタの設定を学びましょう。 ・デジタル信号処理の実践編 1.テスタのマスタクロック(システム例) 2.AWGのサンプリングクロック設定 3.デジタイザのサンプリングクロック設定 4.サンプリングクロック、サンプリング数と測定周期の設定 5.FFTによるスペクトラム分析 6.マルチトーンによる信号発生と取り込み 7.高調波とスプリアス 8.分散処理などによるテストの高速化 9.並行処理によるテストの高速化 1.テスタのマスタクロック 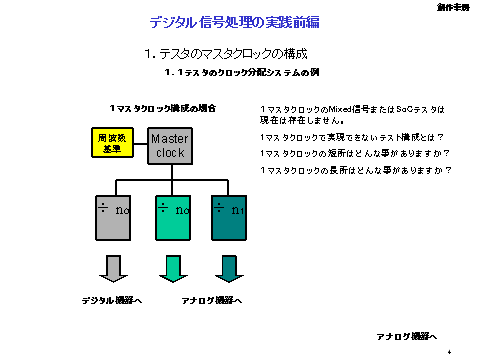 ・テスタの歴史の中に現れた構成で現在ではあまり使われていません。 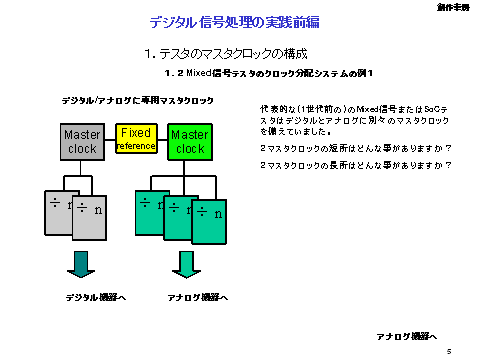 ・代表的な(1世代前の)のMixed信号またはSoCテスタはデジタルとアナログに別々のマスタクロックを備えていました。 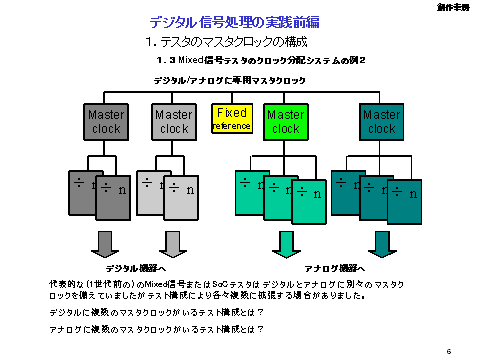 ・代表的な(1世代前の)のMixed信号またはSoCテスタはデジタルとアナログに別々のマスタクロックを備えていましたがテスト構成により各々複数に拡張する場合がありました。 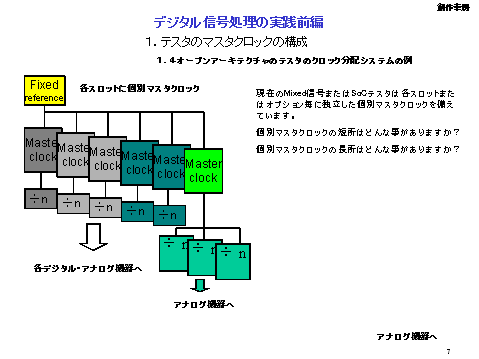 ・現在のMixed信号またはSoCテスタは各スロットまたはオプション毎に独立した個別マスタクロックを備えています。 2.AWGのサンプリングクロック設定 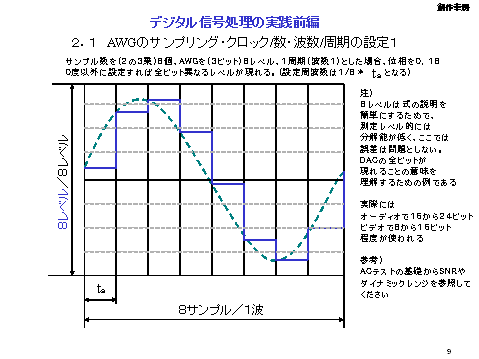 ・AWGのサンプリング・クロック/数・波数/周期の設定1 注)8レベルは式の説明を簡単にするためで、測定レベル的には分解能が低く、ここでは誤差は問題としない。 DACの全ビットが現れることの意味を理解するための例である。 実際にはオーディオで16から24ビットビデオで8から16ビット程度が使われる 参考) ACテストの基礎からSNRやダイナミックレンジを参照してください 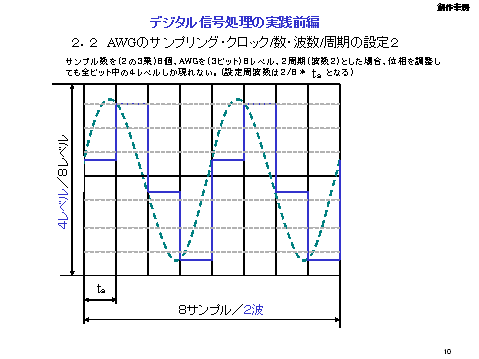 ・AWGのサンプリング・クロック/数・波数/周期の設定2 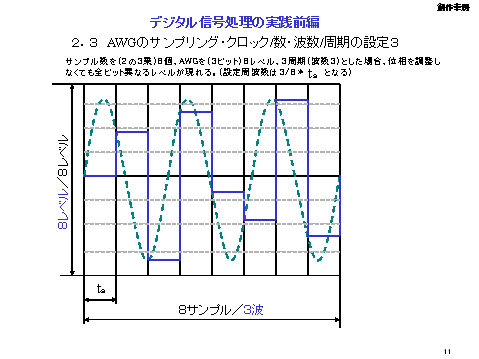 ・AWGのサンプリング・クロック/数・波数/周期の設定3 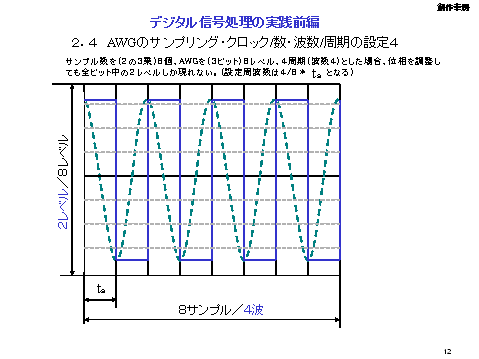 ・AWGのサンプリング・クロック/数・波数/周期の設定4 3.デジタイザのサンプリングクロック設定 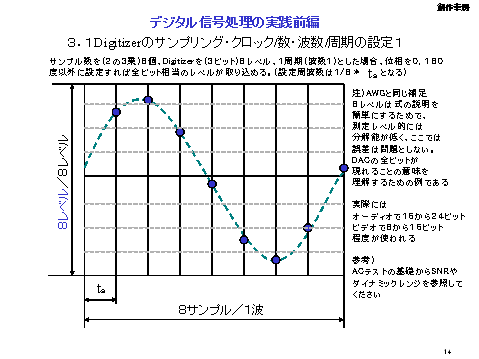 ・Digitizerのサンプリング・クロック/数・波数/周期の設定1 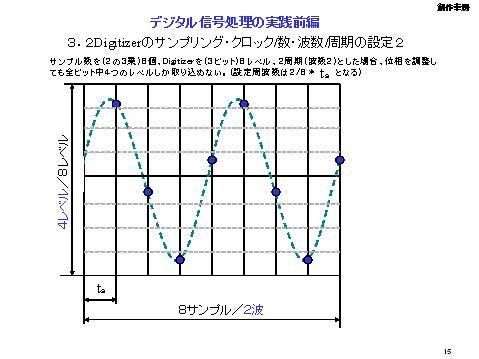 ・Digitizerのサンプリング・クロック/数・波数/周期の設定2 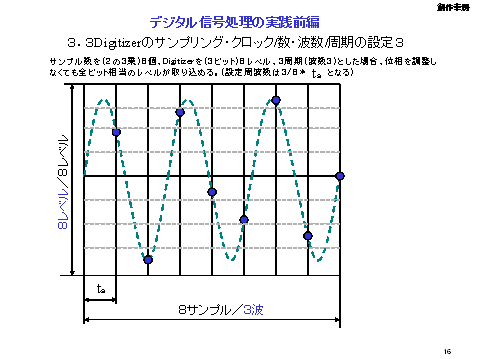 ・Digitizerのサンプリング・クロック/数・波数/周期の設定3 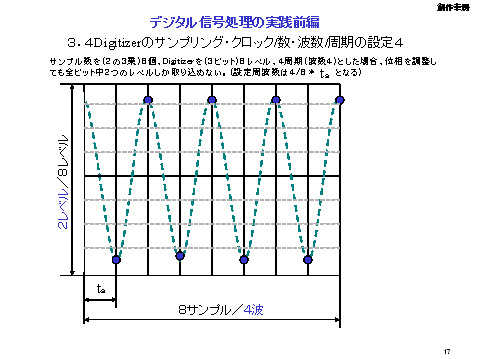 ・Digitizerのサンプリング・クロック/数・波数/周期の設定4 6.マルチトーンによる信号発生と取り込み 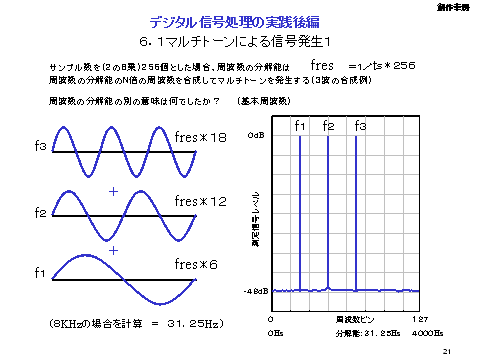 ・マルチトーンによる信号発生1 サンプル数を(2の8乗)256個とした場合、周波数の分解能は fres =1/ts*256 周波数の分解能のN倍の周波数を合成してマルチトーンを発生する(3波の合成例) 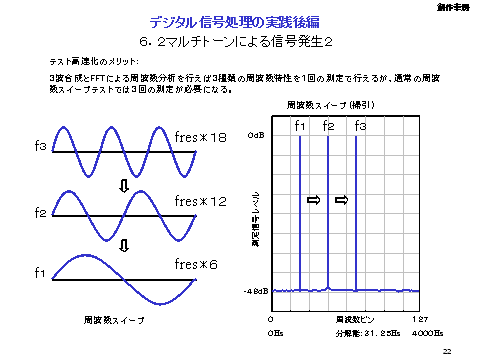 ・マルチトーンによる信号発生2 3波合成とFFTによる周波数分析を行えば3種類の周波数特性を1回の測定で行えるが、通常の周波数スイープテストでは3回の測定が必要になる 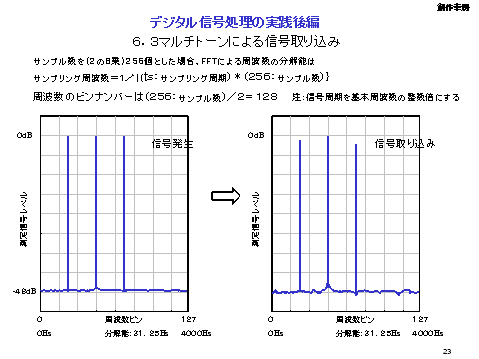 ・マルチトーンによる信号取り込み 周波数のビンナンバーは(256:サンプル数)/2=128 注:信号周期を基本周波数の整数倍にする 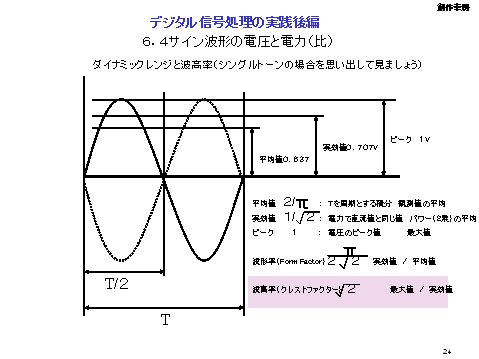 ・サイン波形の電圧と電力(比) ダイナミックレンジと波高率(シングルトーンの場合を思い出して見ましょう) 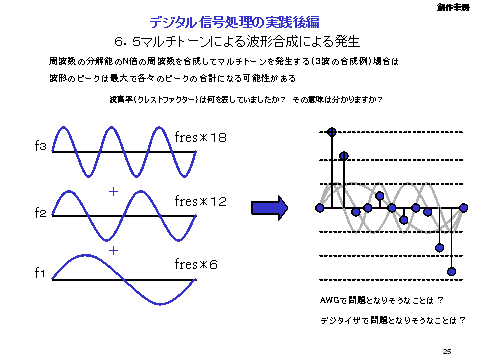 ・マルチトーンによる波形合成による発生 周波数の分解能のN倍の周波数を合成してマルチトーンを発生する(3波の合成例)場合は波形のピークは最大で各々のピークの合計になる可能性がある 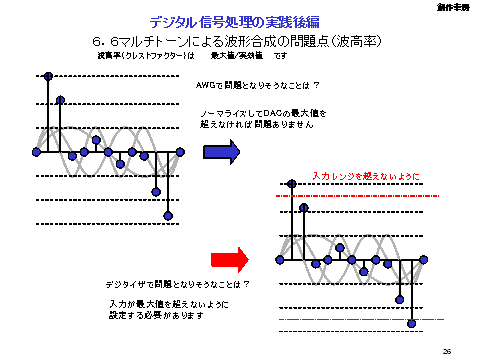 ・マルチトーンによる波形合成の問題点(波高率) 波高率(クレストファクター)は 最大値/実効値 です 7.高調波とスプリアス 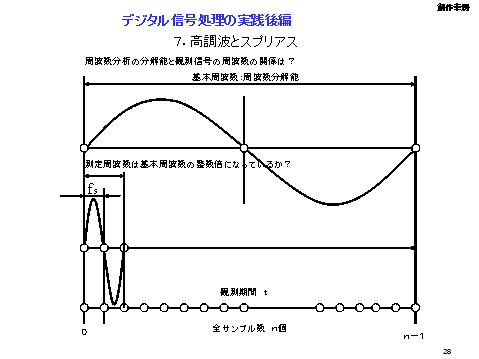 ・高調波とスプリアス 周波数分析の分解能と観測信号の周波数の関係 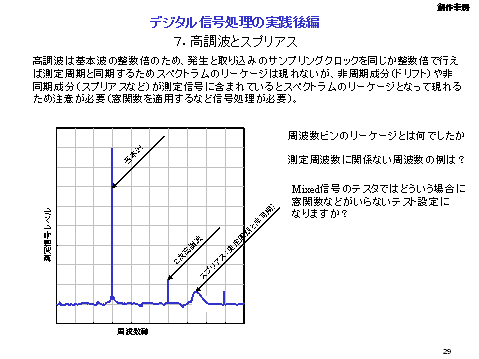 高調波は基本波の整数倍のため、発生と取り込みのサンプリングクロックを同じか整数倍で行えば測定周期と同期するためスペクトラムのリーケージは現れないが、非周期成分(ドリフト)や非同期成分(スプリアスなど)が測定信号に含まれているとスペクトラムのリーケージとなって現れるため注意が必要(窓関数を適用するなど信号処理が必要)。 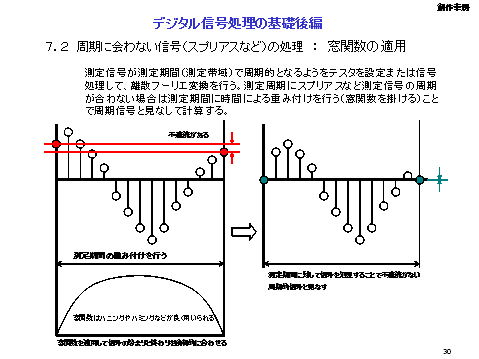 ・周期に合わない信号(スプリアスなど)の処理 : 窓関数の適用 測定信号が測定期間(測定帯域)で周期的となるようをテスタを設定または信号処理して、離散フーリエ変換を行う。測定周期にスプリアスなど測定信号の周期が合わない場合は測定期間に時間による重み付けを行う(窓関数を掛ける)ことで周期信号と見なして計算する。 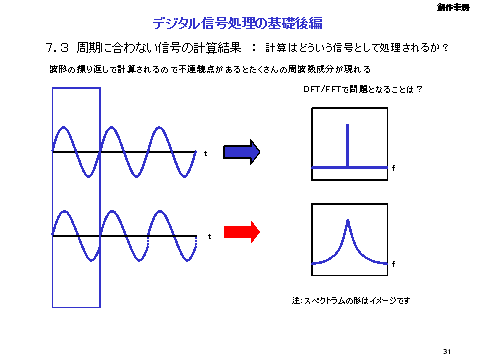 ・周期に合わない信号の計算結果 波形の繰り返しで計算されるので不連続点があるとたくさんの周波数成分が現れる 8.分散処理などによるテストの高速化 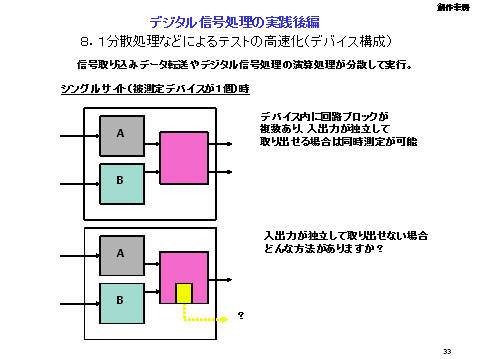 ・分散処理などによるテストの高速化(デバイス構成) 信号取り込みデータ転送やデジタル信号処理の演算処理が分散して実行。 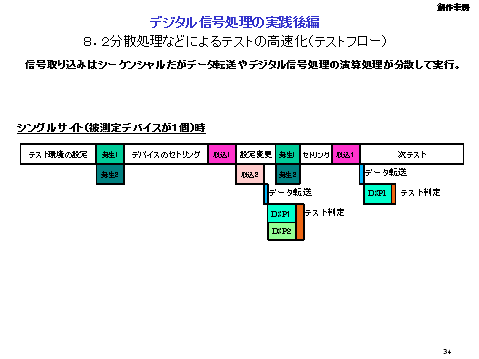 ・分散処理などによるテストの高速化(テストフロー1) 信号取り込みはシーケンシャルだがデータ転送やデジタル信号処理の演算処理が分散して実行。 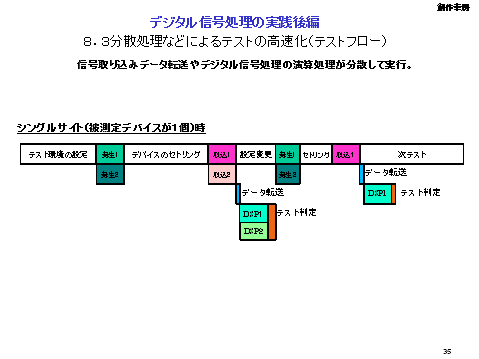 ・分散処理などによるテストの高速化(テストフロー2) 信号取り込みデータ転送やデジタル信号処理の演算処理が分散して実行。 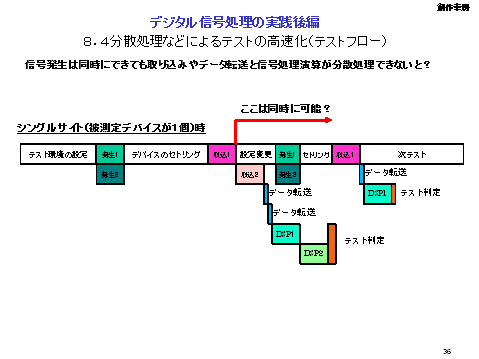 ・分散処理などによるテストの高速化(テストフロー3) 信号発生は同時にできても取り込みやデータ転送と信号処理演算が分散処理できないと? 9.並行処理によるテストの高速化 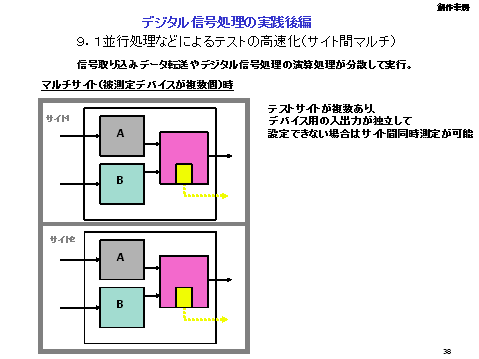 ・並行処理などによるテストの高速化(サイト間マルチ) 信号取り込みデータ転送やデジタル信号処理の演算処理が分散して実行。 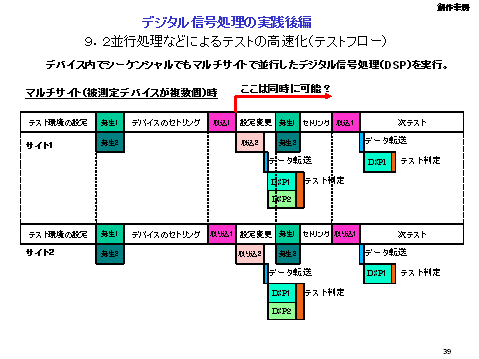 ・並行処理などによるテストの高速化(テストフロー1) デバイス内でシーケンシャルでもマルチサイトで並行したデジタル信号処理(DSP)を実行。 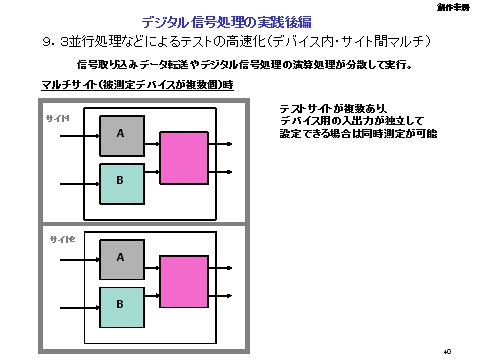 ・並行処理などによるテストの高速化(デバイス内・サイト間マルチ) 信号取り込みデータ転送やデジタル信号処理の演算処理が分散して実行。 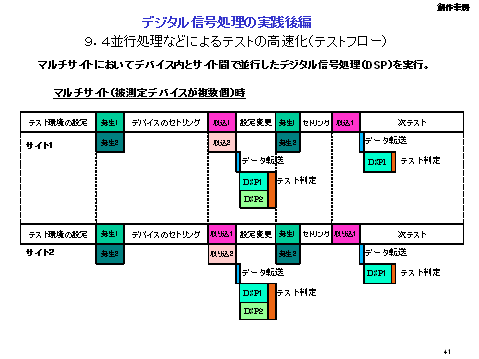 ・並行処理などによるテストの高速化(テストフロー2) マルチサイトにおいてデバイス内とサイト間で並行したデジタル信号処理(DSP)を実行。 資料の活用に関してはご自身の責任で判断いただけますようお願いいたします。引用する場合はソースを明示していただけますようお願いいたします。 |
| 復習2:半導体量産工場で使われている典型的なテスター構成例 デジタル信号処理の基礎を実際に使えるように典型的なテスター構成を復習しておきましょう: (この構成例は以前の創作幸房のデジタル信号処理セミナーにも掲載しています。すでに読まれている方は読み飛ばしてください) 1.デジタル信号処理ソース・キャプチャのアーキテクチャ 2.デジタル信号処理演算のアーキテクチャ 3.デジタル信号測定演算構成 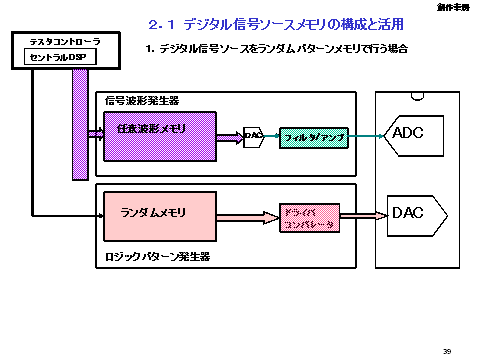 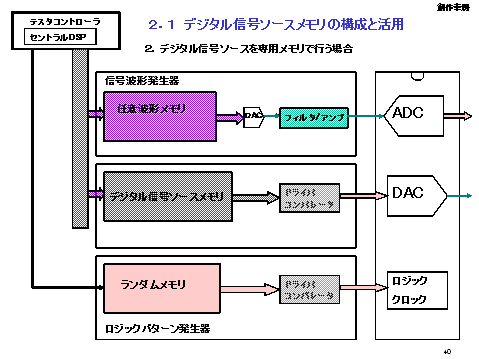 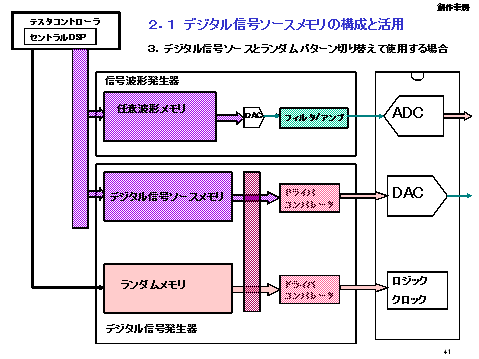 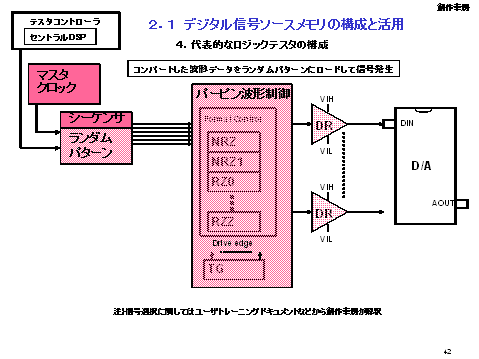 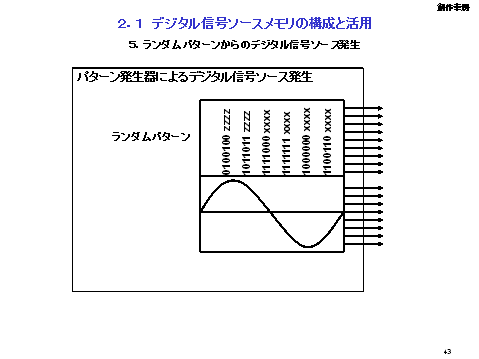 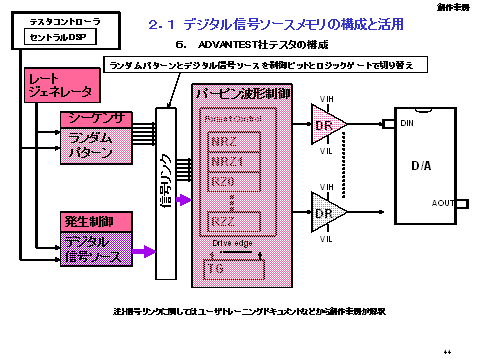 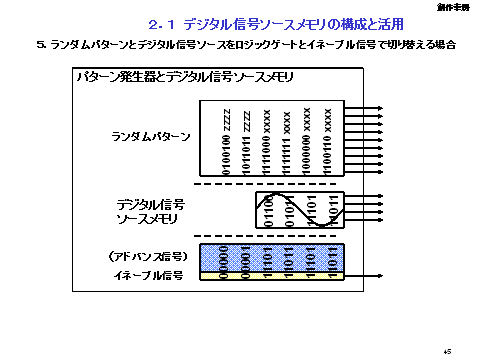 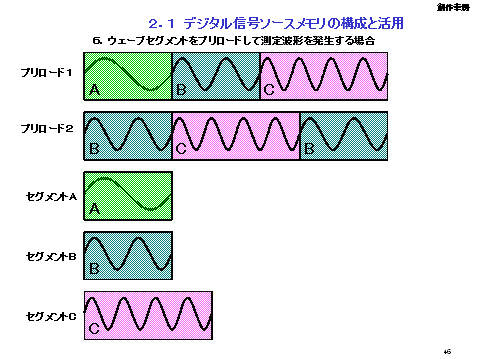 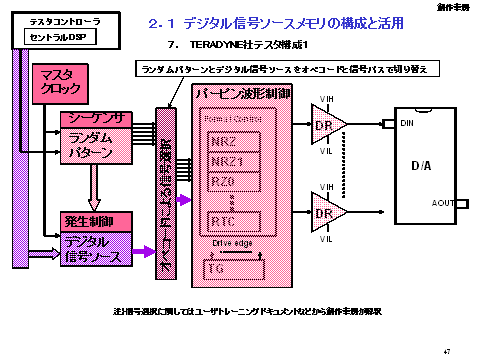 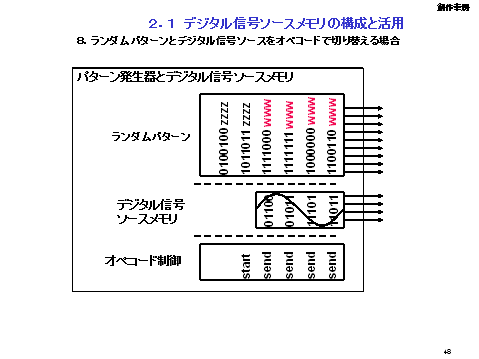 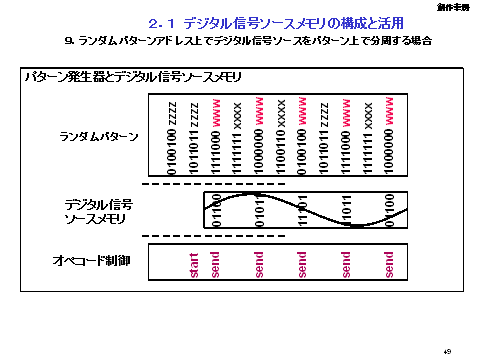 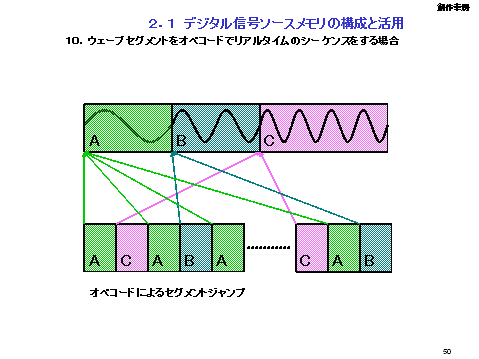 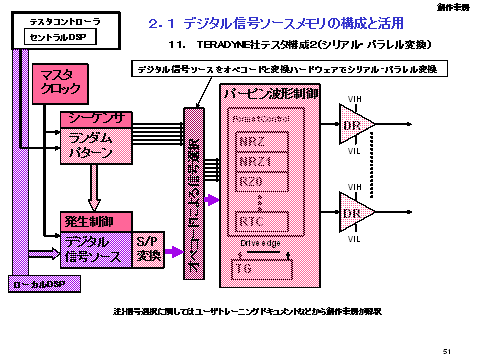 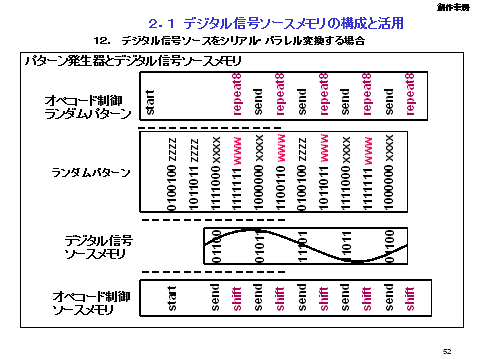 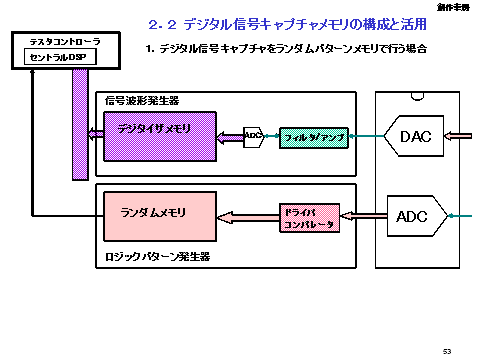 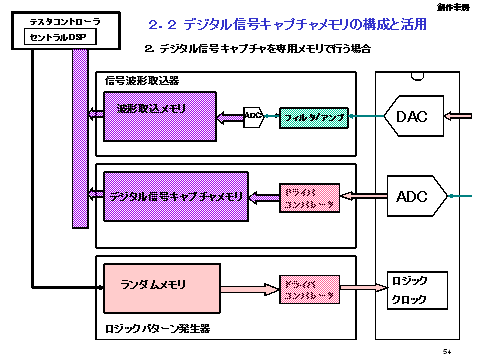 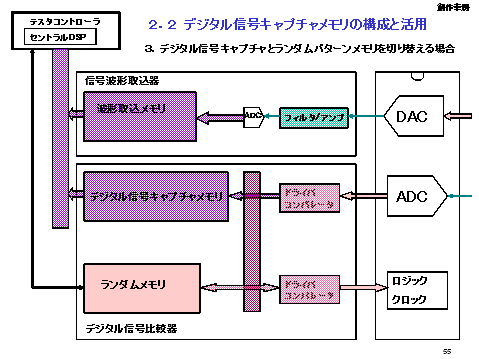 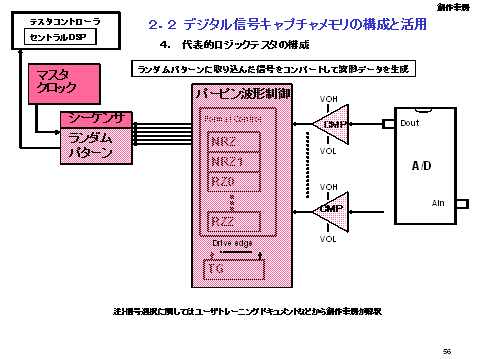 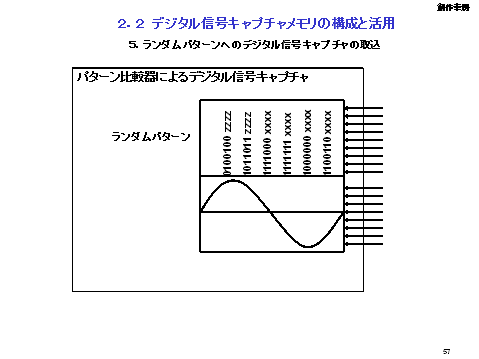 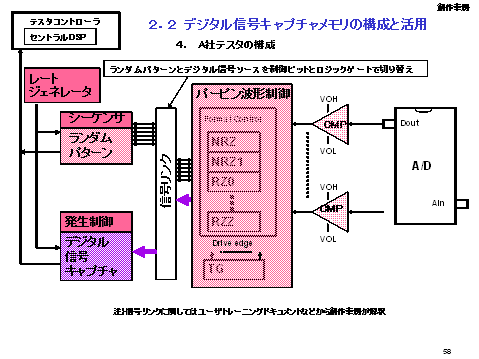 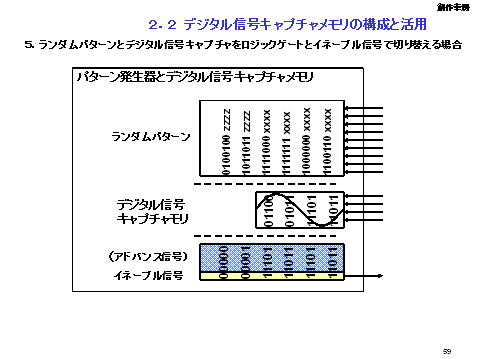 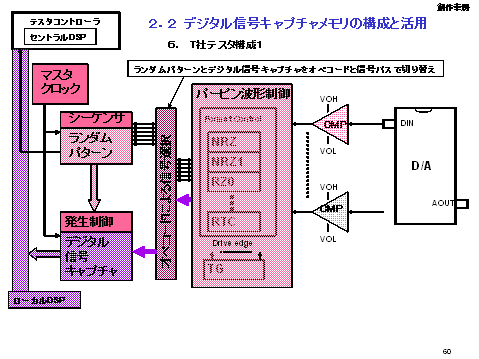 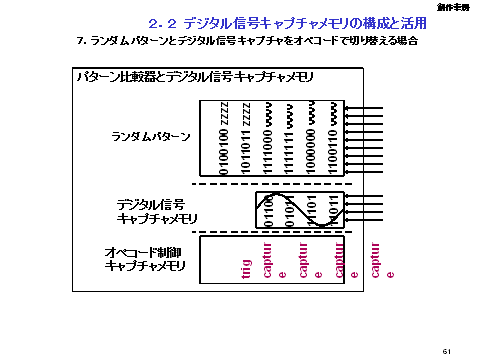 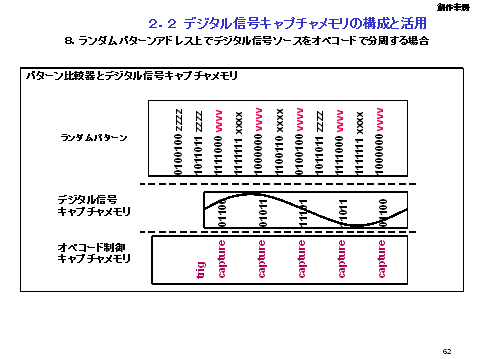 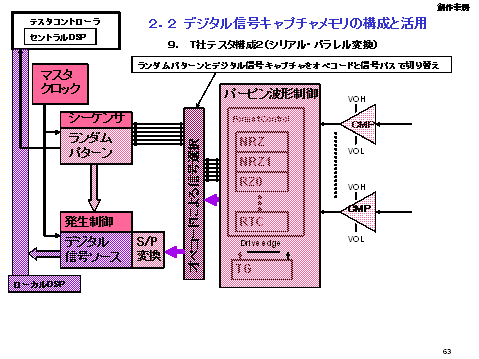 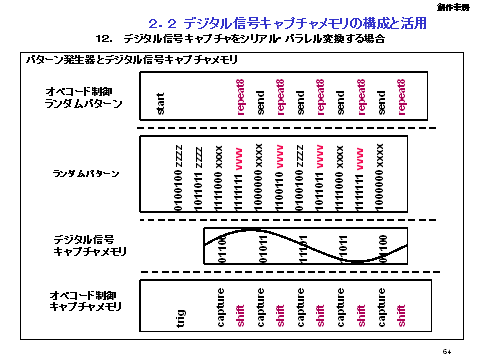 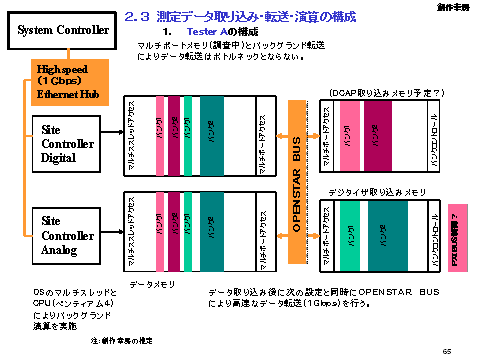 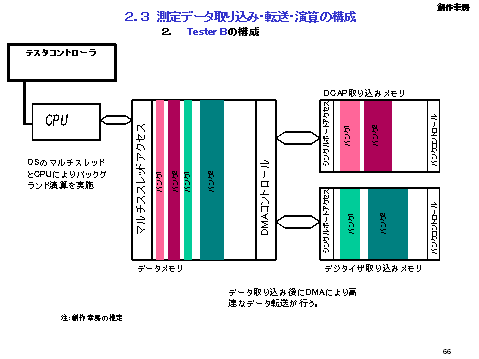 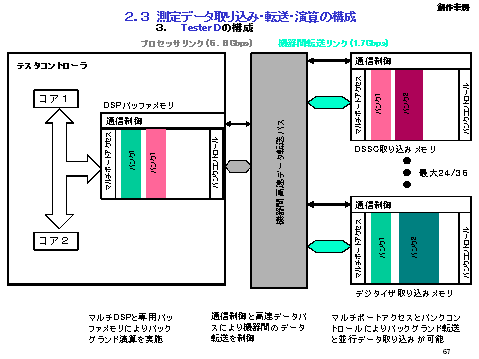 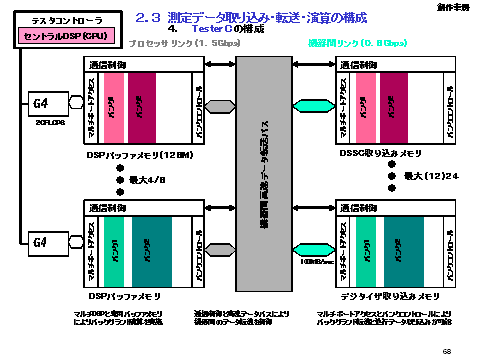 資料の活用はご自身の責任で判断いただけますようお願いいたします。 |
このサイトが、実際にあなたの目的達成のお役に立てれば幸いです。
あなたが目的を達成され、次のステップへと向かわれますように応援しています。
ご意見とフィードバックをいつでも歓迎しております。
掲載ガイドライン
学習には個人差があります。サイトの訪問者の方に誤解を与えたり不快感を感じるような誇大な表現は極力排除するように努めております。出来る限り事実をお伝えし、目的達成に少しでも貢献できますように改善に努めて参ります。また使用に関する結果にはご自身の責任で対応していただけますようお願いいたします